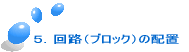
5.1 同一回路における配置
基本的に下記のような順序で回路送りするのが良いでしょう。
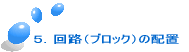
5.1 同一回路における配置
基本的に下記のような順序で回路送りするのが良いでしょう。
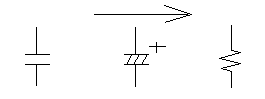
5.2 ブロック配置
文字どおり部品の配置、パターンの流れは回路図が耐ノイズ性を考慮したものであれば回路図の流れ
(信号、電源の供給の流れ)通りに作成するのが基本です。
特にノイズに関連深い部分として
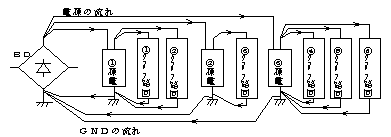
電源は各ブロック単位で供給し、GNDは各ブロック単位で戻すのが基本です。
このうちGNDは回路の電圧基準点であり、わずかなノイズでトラブルの原因となりやすいため、
特にGNDの方に注意をはらう必要があります。
(各回路ブロック単位で電流経路を形成すれば配線を通しての相互影響は少ないと考えられます)
しかし、実際のパターン設計ではこのように配線することはなかなか難しいのが実状です。
従って、上図の流れにする考えを基本において、相互影響の少ない範囲で回路ブロックの統合を考える
必要があります。
ノイズを最小限に抑えるためにもGNDを最低限3系統に分類するのがいいでしょう。
ノイズ源を持つGND、(2)ノイズの影響を受けやすいGND、(3)大電流回路、又は微少電流回路
のGND
ノイズを受けて一番困るのはマイコン周辺の回路であり、ノイズの影響を一番与えるのはスイッチィング
電源等の回路であったり、サーボモータ等の大電流の回路です。
従って、各系統のGNDは他の系統のGNDと交わることなく、パターンの流れを別にして回路の元GND
またはFrame GND(FG)に戻す必要があります。
通常、GNDパターンは最低でも幅1.5~2.0㎜近辺で設計しますが、系統の異なる回路の場合には例えパターン
幅が1㎜程度になっても上記のように分離するのが望ましいでしょう。
(幅についての根拠は特にないですが、インピーダンスを最小限に抑え、現実の設計ではスペースに限り
がありますため、あまり太くはできないでしょう。どちらにしても、実際のパターン幅を決めるのは各種
評価試験の結果によります)
<アナログ回路とデジタル回路の分離>
アナログ回路とデジタル回路は分離するのが賢明です。デジタル回路のノイズがアナログ回路に侵入し
てトラブルの原因になります。
<対策案>
①回路ブロックの分離。
②電源パターンの分離。
③アナログ回路GNDのベタアース化。
<ベタアースについて>
・ディスタンス法(逆貼り)によるパターン形成はベタアースの方向にもっていきやすくなります。
本貼りの場合でも空間(沿面)部にパターンを形成させてその部分をGNDに接続させればベタアースに
近い状態が作れます。熱伝導(放熱)の面でもメリットがでます。