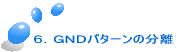
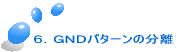
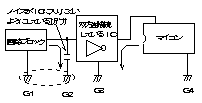
ICの入力部に入れるノイズ吸収用のコンデンサのGND(G2)には十分落ちきらないノイズがあるとみてG1とG2は
同じブロック内に収め、ICのGND(G3)はそのG3にノイズが乗ることによってマイコンに影響を与えるか与えないか
を判断してG4側にもっていくかどうかを決めなければなりません。
例えば、TRアレイのように回路ブロックの電流を引き込む回路についてはG3をG1及びG2側に接続してノイズ分が
マイコンにはいらないようにG4と切り離します。逆に、マイコン側から電流を引き込む4049のような場合にはG3に
ノイズ分は余り乗らないと考えられ、マイコン側のG4と同じGNDに出来るようですが、ICの入力コンデンサのG2と
かなり遠いパターンとなることが考えられ、共通インピーダンスによるパスコン効果が薄れ、ICに余計ノイズ分が
入りやすくなります。かと言って、G3をG1側に接続するとマイコン側から引き込んだ電流が逆にG3→G1(G2)→G4
を通じて(G1→G4間は共通インピーダンス)ノイズ分がマイコンに入ってくることが考えられます。
従って、どちらが良いかという判断からすれば後者のG3をマイコン側に接続するのが無難といえるのではないでしょうか。
全体を通じて言えるのは電流の流れ方向から考えて影響の少ない方に接続するのが基本です。
場合によっては、各GNDを分離して、元GNDで統合する方法もあります。
<オペアンプの場合>
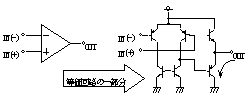
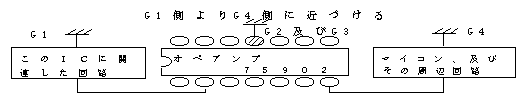
<トランジスタアレイの場合>
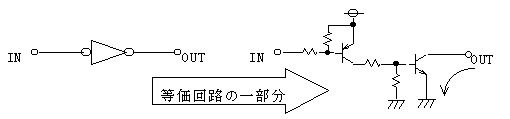
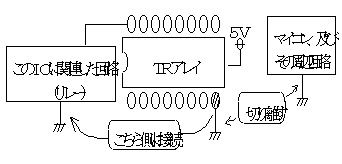
<マイコンに関連したノイズ対策>
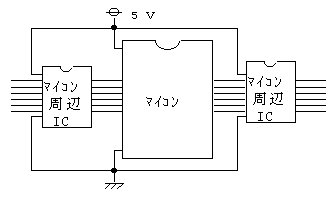
①基本的な知識
・マイコンの端子で反応の早い(敏感)端子ほどノイズに注意を要します。
弱い端子 … INT・NMI端子、RESET端子、I/O端子。
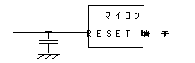
RESET端子は一般的に高抵抗高インピーダンスであるためノイズに弱い。(高インピーダンスでない場合もある)
従って、コンデンサを入れて高抵抗低インピーダンスにします。
・一般的にはクロック周波数が6MHZ以上になると基板を多層にしなければならないほど弱い状態になります。
・I/Oポートを空き端子で放置するとノイズが侵入しやすくなるのでプルアップ、叉はプルダウン処理するの
が望ましいでしょう。(ソフト的に行なうこともできます)
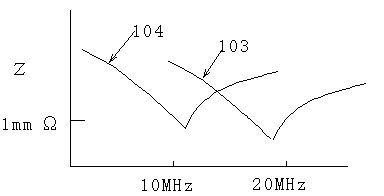
パスコン部品(リード線等含む)の周波数特性は一般的に上図のようになり、103の場合20MHZ以上になるとL分
として働きC分でなくなります。
パターンが長くなるとL分のインピーダンスが増えて共振点が低い方へ移動すると同時にインピーダンスも高くなります。
コンデンサの働きがうすれます。
②具体的な対策
・入力ポートに制限抵抗を入れればノイズ電流を制限できます。
回路定数はマイコンにより変えます。
・発振子のクロックにノイズが入るとマイコンが誤動作したり暴走の原因になります。
周波数が高いため、パターンのインピーダンスが高くなり、外部誘導ノイズが乗りやすくなります。