![]()
実装技術に関わる情報を下記の目次に従って作成しています。
詳細情報の必要な方はこちらまで。
![]()
プリント配線板の実装を考える場合には、実装lifeとして捉える必要があります。
回路仕様に合う電子部品、機構部品の採用に始まって、販売された商品が亡くなるまでの一生(寿命)
を通して、QCDを考えながら取り組むことになります。
電子部品の特性、コスト→部品の形状→部品端子の状態→基板そのものの種類、特性、等→部品の実装
の仕方→半田付け状態→部品、生産ラインの環境面→生産ラインの設備、工程の条件→基板設計→基板試作、
量産→組立、半田付け→検査→製品への組み込み→検査→出荷→市場での使用→ユーザーの反応→故障対応
(メンテ)→廃棄→(リサイクル)
これら一連のlife工程において、ほとんどの仕様を決定するのが、機構設計、回路設計、基板設計と
いった設計部分です。即ち、設計は製品life、実装lifeの扇の要といえます。
これらの観点にたち、マニュアルをまとめています。
あらゆる機器の制御回路を実装設計する場合に求められるものは、(1)回路の機能を満足させる、(2)低コストの
基板に仕上げる、(3)実装工程において如何に生産性を高くして低コストで生産できるか、そして、(4)全工程を通じて
品質の高い実装基板に仕上げる、の4点に尽きると考えています。これを達成することが競合他社に打ち勝つことに
もなり、21世紀に安定して成長できる実装技術と考えています。
この手順書が、その参考的役割を果たせれば幸いです。
20年余りの間この実装設計分野に身をおき、その中から得たノウハウを順序立てて説明したいと思います。実装設計
というのはご存じの通り、プリント配線板自体の設計が全てではありません。その前後に関わる技術全てが絡み合って
出来上っています。従って、設計するのにも物の流れ全てを熟知した上で行わなければ、その設計は自己満足の域を
脱し得ない結果に終わる、と言っても過言ではありません。そういった意味で、この手順書は、前半に設計のために必
要な周辺業務を記し、後半に設計のやり方を関連づけて記す形にしています。そうすれば、設計が物の生産の中で扇
の要的役割を果たしていることが充分理解していただけると考えています。
プリント配線板に回路を構成するのにも、片面銅張積層板の上に配置する場合、両面銅張積層板の上に配置する場合、
多層銅張積層板の上に配置する場合、等様々な方法が考えられます。
どの方法にするかは、ノイズに強くして回路の機能を満足させるためとか、価格を安くしたいとか、いろいろな要求に応
じて決定されます。
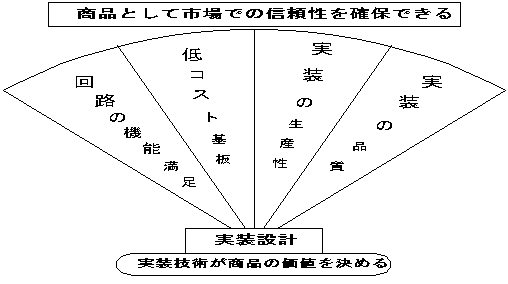
プリント配線板の実装を考える上では、実装LIFEとして捉える必要があります。
回路に使用される電子部品、機構部品に始まって、販売された商品が亡くなるまでの一生(寿命)を通してQCDを考えながら
取り組む必要があるということです。
電子部品の特性、コスト→部品の形状→部品端子の状態→基板そのものの種類、特性、等→部品の実装の仕方→半田付け
状態→部品、生産ラインの環境面→生産ラインの設備、工程の条件→基板設計→基板試作、量産→組立、半田付け→検査→
製品への組み込み→検査→出荷→市場での使用→ユーザーの反応→故障対応(メンテ)→廃棄→(リサイクル)
これら一連のLIFE工程において、ほとんどの仕様を決定するのが、回路設計、機構設計、基板設計といった設計部分です。
即ち、設計は製品LIFE、実装LIFEの扇の要といえます。
これらの観点にたち、以下、まとめています。
<お断り事項>
このマニュアルは、世の中の多種多様商品群の中において、ある分野に限定した内容であります。
お取り引き先の顧客に対しては、機密保持の原則にたって、業務に当たっておりますので、顧客の情報がこのようなマニュアル
的な形で、掲載されることは決してありません。
あくまで弊社担当のセットメーカーにおける長年に渡る経験の一部を掲載しておるものとご理解願います。
![]()